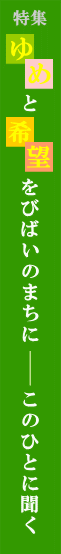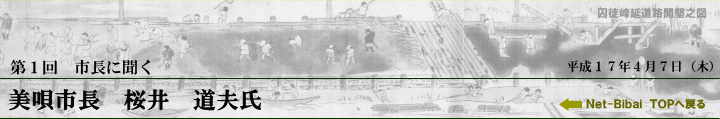 |
|
|
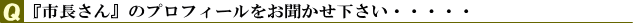 |
| A. |
| (生年月日は?) |
・・・・・・ |
昭和24年11月8日美唄生まれ |
| (血液型は?) |
・・・・・・ |
O型 |
(休日はどんなことをして
過ごされていますか?) |
・・・・・・ |
市長になると土曜日も日曜日も、いろいろな行事があるので、出かけて行きます。
たまに仕事がないときが休みになります。そんなときは休養をします。 |
| (趣味は?) |
・・・・・・ |
カラオケ−山本譲二の「おまえと生きる」が十八番。 |
| (ご家族は?) |
・・・・・・ |
現在は奥様と2人暮らし。長男長女は独立。 |
| (座右の銘は?) |
・・・・・・ |
誠心誠意 |
|
|
 |
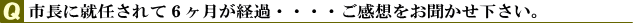 |
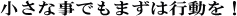
|
| A. |
市の職員を経て、昨年10月に市長へ就任致しました。
私は、昨年の選挙活動などを通じて、多くの市民の方々とお話しをさせて頂く機会を得て、この時代は、本当に『市民の方々がご苦労されている』、という事を痛感致しました。市長として、市民の皆様の生活を守り、住み良いまちになるよう、今後の 市政に反映させていかなければならないと感じました。特にこのことは市の職員が今以上に『市民の大変さを理解』し、市民にとって今、市役所がなすべき事は一体何なのか、何が必要か、そのために、職員が何をしたら良いのか、その辺りの意識をしっかりともって頂きたいと感じています。
この6カ月は、美唄市のあらゆる課題に直面し、行動して参りましたが、厳しい財政の中でも、お金をかけずに出来ることは、色々あると思っています。市民の皆様にも積極的に行政に参加して頂くと共に、市職員が市民のためにできる事を考え、それを行動にうつして頂ければと思っています。 |
|
 |
|
 |
 |
 |
| A. |
現在、設置のため、検討中の『食の駅』では、『ハーブ米』『雪蔵工房米』或いは『アスパラ』などの農産品、そして『米粉で制作したパン、麺、お菓子』、や、全国一の収穫量を誇る『ハスカップ』などの農産加工品、『やきとり』、『とりめし』などを販売したいと考えております。
この『食の駅』では、美唄の基幹産業である、農業を主体とした農産物やその加工品を、売るわけですが、このことで、美唄の商工業、飲食業なども同時に活性化されると思っております。『食の駅』をきっかけに商工へと波及させるわけです。1次産業に付加価値をつけて、2次、3次産業へ・・・これが美唄のまちづくりのきっかけになると考えています。米粉は小麦粉の代替として利用価値があり、現在調査、研究中ですが、将来の展望は明るいと感じています。
|
|
|
|
動画が再生されない場合は更新ボタンをクリックして下さい。 |
|
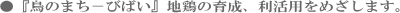 |
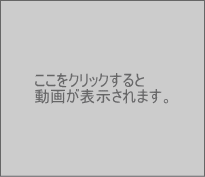 |
A. |
また、地鶏をこの美唄で育て、それを利用した美唄ならではの、『やきとり』『とりめし』も魅力があると思っています。例えば焼き鳥サミットを美唄で行うなど、マスコミなども、巻き込み、全国的に有名になれば、と思っています。
役所内に『交流推進室』を設置したのも、こうした『食の駅』を通じた『交流人口』を増やし、美唄全体を活性化したいと考えているからです。
|
動画が再生されない場合は更新ボタンを
クリックして下さい。 |
|
|
|
|
 |
|
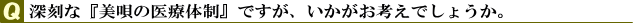 |
 |
 |
 |
A. |
市民の皆さんが今、最も不安を持たれているのが、医療問題と思います。
皆さんが安心できる地域医療のあるべき姿を明確にして、これに基づいた取組みを進めていく上での指針として、現在『地域医療ビジョン』を策定しています。このビジョンは、市議会の『地域医療問題等調査特別委員会』でのこれまでの議論経過や医師会などからいただいたご意見等を踏まえ、今ある市内の医療資源を生かした新しい総合病院づくりを基本に策定作業を進めています。
|
|
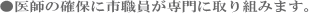 |
| A. |
また、医師不足が深刻化していますが、地域医療を確保するためには、医師の確保が最優先課題と考えています。大学への要請や民間の人材紹介会社の活用はもちろん、医師会をはじめ、あらゆる人脈を通じて医師の確保に全力で取り組んでいきます。これまでも、こうした考えで色々やってきましたが、4月からは、市立病院の医師確保のために、部長職の担当理事を配置して、今お話したことを専門に取り組むこととしています。
|
|
 |
|
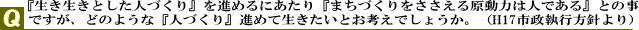 |
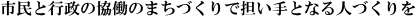 |
 |
| A. |
国では、『官から民へ』、『国から地方へ』という方針のもとに構造改革が進められ、地方を取り巻く環境は、地方分権をはじめ、三位一体の改革や規制緩和など、大きな転換期を迎えています。市民も市役所も、国に依存していた状態から脱却し、自らの責任と選択によるまちづくりが求められており、市民、企業、NPO等と市役所が対等・協力の下に、一体となってまちづくりに取り組んでいく必要があります。
|
|
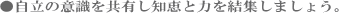 |
| A. |
本市は自立の道を選択しましたが、経済、雇用など様々な局面において、かつて経験したことのない重大な試練の時を迎えています。この試練に立ち向かっていくためには、すべての市民の皆さんが自立するという意識を共有し、地域の持つ知恵と力を結集することが何よりも大切と考えます。
そのためには、地域の特性や社会資源を活かして、例えば、『間口除雪』や『子育て支援』など日々の生活に密着したサービスを市民の皆さんと行政が協働して創り上げることが必要です。私は、こうした仕組みを互いに汗かきながら創り上げていく中で、まちづくりの担い手となる人づくりを進めていきたいと考えております。
|
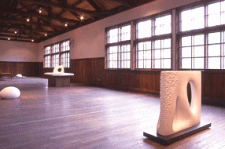 |
|
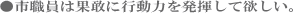 |
| A. |
また、職員には、『理論、理屈より行動を』と言っております。『行動することで少しでも結果を出すことが大事』という考えだからです。時には走りながら考える事も必要です。一般的に『大過なく仕事を終えた』と、いう仕事の満足感を表現する場合がありますが、私は、大過なくというのは、何もしないことに等しいと考えておりますので、失敗を恐れずに果敢に挑戦していくことが大変重要と考えており、職員にもこのような視点で仕事を進めることを求め、事あるごとに話をしていきます。
|
|
 |
|
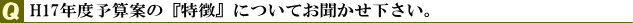 |
 |
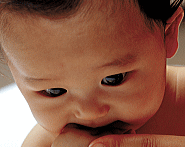 |
A. |
私は、市政執行方針の中で、『生き活き美唄の実現』、『地域医療体制の構築』、『自立の取組み』、『協働のまちづくり』を基本にまちづくりを進めることを述べました。
主な取組みを申し上げると、少子高齢化が進む中で市民相互の支え合いや地域との協働による社会参加の仕組みづくりや親子に絵本を贈るブックスタート事業、仕事と子育ての両立を支援するため、子育て地域支え合い事業を実施します。 |
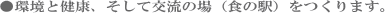
| A. |
また、自然環境の保全に配慮した新しい最終処分場の整備に着手しますし、循環型社会の構築に向け、廃棄物の発生抑制や再資源化に取
り組みます。本年5月にはパークゴルフ場がオープンしますので、本市の豊かな地域資源相互の連携による多様な交流の展開を図ります。
また、『食』をテーマにした『道の駅』の整備に向けて調査・研究を進めるほか、米粉利活用の定着を図るため、学校給食への米粉製品の導入調査や加工事業者等による組織づくりを進めます。このように、福祉、環境、交流、そして経済振興に重点をおいて取り組んでいきます。
道の駅は、温泉施設や日本一の直線道路をはじめ、自然、産業、文化、特産品などの地域資源を活かして、相乗効果が生まれるような活動を展開するため、国道12号線沿いに『食』にこだわったものをつくります。道の駅の周辺には農産物の加工施設や販売施設をつくり、美唄ブランドの開発とPRを積極的に行うことで、通過するまちから立ち寄ってみたいまちになるよう、魅力あるまちづくりを進めます。場所や規模、運営主体などは、今後、調査・検討していきます。 |
|
 |
|
|